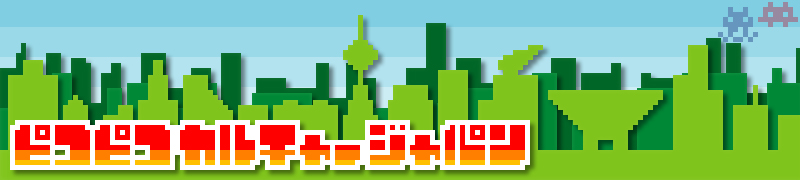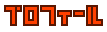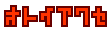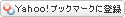「1999」第1章
第8話「鈴木」
そのメイド喫茶は、本当にマジでどうっっっっっっっっしょうもない最低クオリティの店だった。
というか、正直ただの喫茶店である。
ドアを開けた瞬間、目に飛び込んできたのは、くすんだモスグリーン色のカーテンと、針金入りの擦りガラスと、所々がガムテープで補強してあるエアコンと、枯れかけている観葉植物、申し訳程度にメイドのコスプレをした眼鏡っ娘が一人だった。
否、「眼鏡っ娘」という表現は不適切である。「娘」ではなくて「女」だ。「眼鏡女」が正しい。
眼鏡女はブサイクというわけではない。どちらかと言えば整った顔立ちをしていると思う。だが、「萌え」や「キュート」といった形容詞からは程遠い世界の住人である。そういう女だ。
「あ、いらっしゃいませー♪」
奥のカウンターで皿を磨いていたマスターが出てきて、僕達を暖かく迎えてくれた。眼鏡女の方はといえば「お帰りなさいませ☆ご主人様ぁ」はおろか「いらっしゃい」の一言すら発しない。
むっつりとした顔で自由箒を握りしめ、黙々と床を掃いている。果してこの女を「メイド」と呼んで良いものかどうか―――僕は36秒程悩んだ。
とりあえず僕達はテーブル席に座り、メニューを手にした。で、僕は「愛情たっぷりラブラブオムライス」を注文し、井上は「ウキウキワクワク☆ドキドキはんばーく」とやらを注文した。
明らかにヤバい感じのするメニューだが、半日歩きまわったせいで空腹は絶頂に達している。この際、口に入れられるものであれば何だっていい。今なら革靴の底だって食べられる気がする。
数分後、僕達の前に現れたのは、何の変哲もないオムライスとハンバーグだった。
食べてみると、普通に旨かった。だが、別段「愛情たっぷり」でもなければ「ラブラブ」でもない。ハンバーグの方も何が「ウキウキワクワク」なんだか分からないし、ちっとも「ドキドキ」しない。マスターのおっさんが作った、単なるオムライスであり、ハンバーグである。それなのに値段はメイド喫茶相場で割高となっている。
だが旨い。猛烈に腹が減っているせいもあるが、その影響を差し引いても、かなりハイレベルな部類に入るオムライスだった。ハンバーグの方もちょっとだけ井上の皿から失敬したが、やはり旨い。プロの仕事である。マスターは何処にでも居るようなオッサンと見せかけて、只者では無いのかもしれない。実は海原雄山と交友関係があるのかもしれない。
食事を済ますと、メイドの眼鏡女が「水のおかわりは必要か?」と聞いてきた。無論、コケティッシュな猫なで声などではない。場末のスナックのママから発声されそうな、すれっからしのハスキーボイスである。
僕は「ありがとう」と言ってコップを差し出した。恐らくこの機を逃せば、眼鏡女は二度と話し掛けてこないだろう。そうすると、柿原についての情報を聞きだす事は不可能となる。
「あのさ…」
「何?」案の定、眼鏡女はギロリとこちらを睨みつけ、不機嫌そうに返してきた。思ったより手強い。
「一ヶ月前のことなんだけど――――この店で『ほっかほかのココア』なるメニューを注文した奴がいた筈なんだが、覚えてないかな…?」
緊張のあまり、微妙な切り出し方になってしまった。頑張れ、僕。
「ハァ?んなもん分かるかっつーの。ていうか一ヶ月前にココア頼んだ客なんて言われてもねぇ。いちいち覚えてるわけないじゃん。常識的に考えて分かんない?」
見事なまでに愛想の欠片もない返答である。ここまで無愛想だと、逆に気持ちがいい。
「悪い。そりゃまあそうなんだけどね。ちょっと事情があってさ、協力して欲しいんだ。」
僕は食い下がり、柿原家で発見したレシートを眼鏡女に見せた。
「4月3日(土)/ 18:13 ほっかほかのココア かぁ・・・。」
「やっぱり分かんないかな?」
「いや、この日の事だったら覚えてるかも。特別客が少なかったから・・・たしか、ココアの頼んだのは常連の―――」
「柿原?」
「そう、その人。柿原さん。」
眼鏡女は、僕の方を向いて肯定した。とりあえず第一関門は突破である。 ていうか柿原、この店の常連だったのか・・・こんなシケたメイド喫茶のどこが良かったんだ?
「そいつ、友達だったんだ。」
「ふうん。友達だった、か。『だった』て事は、今は友達じゃないってこと?まあいいわ。深くは聞かないでおく。
で、そのお友達がどうしたの?」
「死んだ。」
「え・・・?」
「先月の事なんだけどね。奴の部屋を訪ねたら、首吊ってて。泡を吹いて死んでいた。で、僕達はすぐに通報したんだけど、警察は早々と自殺と断定して、捜査を切り上げてしまった。
でも僕はまだ納得してない。何故柿原が自殺しなきゃいけなかったのか、見当もつかないんだ。」
「・・・。」
「そんで、俺達が独自に調査を進めてるってわけ。」
さっきから喋りたくて仕方がなさそうだった井上が、ついに横槍を入れてきた。
「ふむ・・・。」
眼鏡女はレシートと僕達を交互に睨みつけ、しばし沈黙した。何かを考えている様子である。
店内に妙な緊張感が走った。
圧迫面接でも受けているような気分である。まあ僕は、就職活動なんてしたことないんだけど。
数分後、眼鏡女はレシートを僕に返して、言った。
「とりあえず、話だけでも聞かせてもらうわ。協力できるかどうかは、正直わかんないけど。」
「ありがとう。」
僕はレシートを受け取り、眼鏡女に礼を言った。
カウンターの奥にいたマスターが、僕に目配せして、右手の親指を立て、ウインクして、ニヤリと笑った。
口の中から顔を覗かせた歯が、やたらに白く光っていた。
全くもって意味不明のため、とりあえずマスターの方は無視することにした。
(続く)
関連サイト